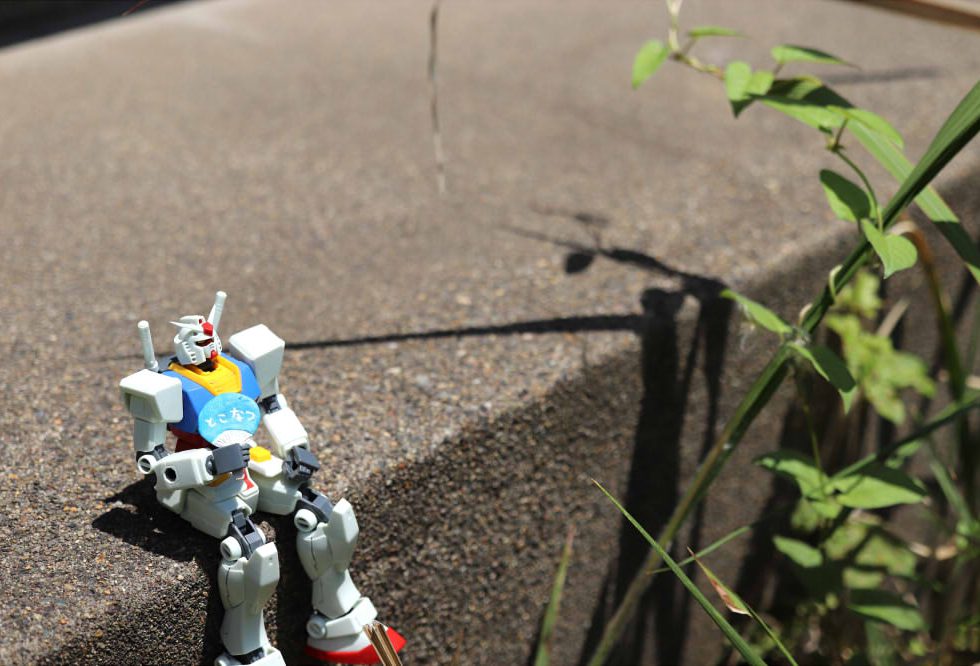こんにちは。
3連休いかがお過ごしでしたでしょうか、ブリテンです。
私はと言いますと、いかんせん台風でしたので、
『ゲーム・オブ・スローンズ』をシーズン7まで見て、
またシーズン1から走りなおす作業をしていました。
人気作なのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、
『ゲーム・オブ・スローンズ』(原題:Game of Thrones)は
アメリカのケーブルテレビ局HBOが制作する、
イングランド・薔薇戦争をモデルとした、ファンタジードラマです。
このドラマ、ウェスタロスと言う大地で
個性豊かな登場人物同士が織り成す群像劇が
とても面白い! 先が気になる!
のですが、
それと同じくらい、背景が素晴らしいです。
ウェスタロス北部の「ウィンターフェル」は北アイルランド
ウェスタロス中南部の王都「キングスランディング」はクロアチア
ウェスタロス最南端「ドーン」はスペイン
で撮られており、それぞれ街の特色を出しています。
特にドーンは中世ヨーロッパ的なことを言えば、レコンキスタ完了前なので、
スペイン+イスラムの雰囲気を出しています。
これらはすべて架空の場所です。
しかし、実際にその場所が世界に存在したら・・・
いやむしろウェスタロスとその周辺諸国が実際に存在したら・・・
という想定で作られているため、リアリティがあります。
その分制作費がハンパないことになっているそうですが、
登場人物やドラマを立たせるためにも、
背景のリアリティも追求しているのですね。
みなさんも、もしご覧になられる際は
「背景」にも注目してみてくださいね。